開催日時: 2025年6月27日(金)13:00~15:30
開催場所: 八雲倶楽部
出席者: 12名
今回の読書会には、三期生で3年以上にわたり読書会を主宰されているAさんが参加してくださいました。これまで読書会で読まれた本の中から6冊をご紹介いただき、運営や本の選び方、討議の工夫など、たいへん参考になるお話を伺いました。
【Aさん紹介の6冊】
◆『ナニカアル』桐野夏生(新潮文庫) 本書は、女流作家・林芙美子の人生を下敷きに、太平洋戦争中に彼女が従軍記者として赴いた東南アジアでの出来事を描いたフィクションです。林は国の命を受けて現地に渡り、そこでかつての恋人の新聞記者と再会するも、待ち受けていたのは戦場の苛酷な現実と、戦意高揚を求められる立場との苦悩でした。桐野夏生は林の人生に寄り添いながら、表現者としての覚悟と、戦争に巻き込まれた女性作家の葛藤を描き出しています。読者に、歴史の影で揺れる一人の女性の視点を通して、戦争の現実と表現の自由を問う力強い作品であり、読売文学賞を受賞しています。
◆『紫式部ひとり語り』山本淳子(角川ソフィア文庫) 源氏物語研究の第一人者である山本淳子氏が、紫式部自身が語り手となって現代の読者に語りかけるというユニークな構成で執筆した作品です。物語を生み出す苦悩や宮廷生活の煩わしさ、藤原道長との関係性、そして女房としての心情の揺れ動きなどが、あたかも本人の口から語られるように展開していきます。従来の学術的な解釈とは一線を画し、源氏物語の創作背景を情感豊かに描く本書は、古典文学への親しみや関心を呼び起こす新しい入門書でもあります。
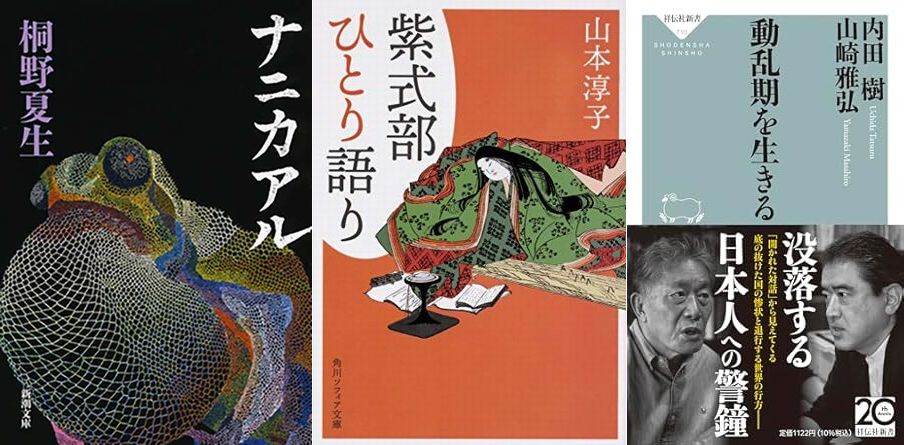
◆『非色』有吉佐和子(河出文庫) 終戦後、黒人米兵と結婚して渡米した日本人女性が、ニューヨークのハーレムで半地下の生活を余儀なくされる姿を描いた衝撃作。人種差別、異文化間の断絶、そして異国の地で生き抜く女性の強さと苦悩が、リアルに描かれています。作者自身のアメリカ留学体験を踏まえて書かれており、肌の色だけでなく、言語や文化の違いも含めて「異なる者」として生きることの厳しさが伝わってきます。
◆『パンとサーカス』島田雅彦(講談社文庫) 全700ページに及ぶ壮大な政治冒険小説。戦後日本の「アメリカの属国」状態からの脱却を目指し、CIAエージェントとなった主人公とヤクザの親友が繰り広げる破天荒な改革運動。国家権力、報道、暴力、友情、そして理想主義と現実主義のせめぎ合いが、エンタメ性を持ちつつシリアスに描かれています。現代日本の閉塞感や欺瞞を鋭く抉るストーリー展開は、インパクトを与えました。
◆『浮世の画家』カズオ・イシグロ(ハヤカワ文庫) 戦中に愛国的な芸術を描いた画家が、戦後は非難の対象となり、自らの芸術と信念を見つめ直す姿を描いた小説。カズオ・イシグロならではの静謐で抑制された文体の中に、深い自省と哀しみが滲みます。戦争をめぐる個人の責任や、時代の価値観の変化、そして老境に至った一人の芸術家の孤独と葛藤が、過去の回想を通して浮かび上がります。
◆『動乱期を生きる』内田樹・山崎雅弘(祥伝社新書) 思想家と歴史研究家による異色の対談形式の書。裏金問題、統一教会、メディアの劣化、そして国民の思考停止。こうした現代日本の問題点を縦横に語り尽くしながら、未来への希望を語る本書は、重苦しい現実のなかにあっても「諦めない姿勢」の重要性を伝えます。両氏は、今の日本が「国としての体をなしていない」としつつも、知性と誇りを持って生き抜くことの意味を説いています。会では「気がつけば我々も少子化や人口減少を含め動乱期に生きている。今後どう行動するかを問われていると感じた」という声などでた。
Bさん
◆『ジーヴズの事件簿』P・G・ウッドハウス(文春文庫) 英国貴族バーティ・ウースターとその名執事ジーヴズの名コンビが繰り広げる、英国流のユーモアと機知に富んだ短編集。お人好しで少し間の抜けた青年貴族バーティが、たびたび社交界や親戚とのトラブルに巻き込まれるものの、ジーヴズの的確かつ鮮やかな解決によって毎度切り抜けるという軽妙なストーリーが展開されます。登場人物たちの洒落た会話、英国ならではの風刺、そしてどこか牧歌的な時代の空気感が魅力で、読む者に安らぎと笑いをもたらします。美智子上皇后も愛読されたとされ、そのエレガントで知的なユーモアは、まさに世代を超えて愛される古典的名作です。
また、Bさんからは最近話題となった「積読(つんどく)」についての新聞コラムの紹介もあり、会では「積読こそが知的好奇心の表れ」といった意見も飛び出し、思わぬ盛り上がりを見せました。
Cさん
◆『世界秩序が変わるとき』齋藤ジン(文春新書) 元銀行員で、現在はアメリカ在住の投資コンサルタントである著者が、金融の現場で得た視点を生かして、アメリカおよび日本における「新自由主義からの転換」について解説した話題書。新自由主義がもたらした格差や経済の停滞、グローバル資本主義の限界を指摘しつつ、ポスト新自由主義時代の新たな価値観や社会構造の可能性を描いています。特に、トランプ政権の出現を「現代の危機」として捉える分析や、日本の経済的・政治的な課題への具体的提言は、読者にとっても大いに参考となります。
〈感想〉 トランプ現象の背景や、日本にとっての転換期についての説明がわかりやすく、示唆に富んでいた。
Dさん
◆『知能とはなにか』田口義弘 人間の知能を単なるIQの数値で捉えるのではなく、より広い視点から多面的に理解しようとする試みである。知能を「環境に適応する力」と捉え、論理的思考や言語能力だけでなく、感情や直観、創造性、社会的判断力といった要素も重要視する。加えて、AIとの比較を通じて、人間固有の知能の特質や限界についても考察される。著者は、知能は生得的な資質に加え、経験や学習を通じて育まれるものであり、多様な知能のあり方を認めることが、教育や社会の在り方にもつながると説いている。知能を固定的なものとせず、発展可能なものとして捉える視点が興味深い。
◆『寿命を自分で決める時代』早野元詞 医療やテクノロジーの進歩によって人間の寿命が飛躍的に延びる現代において、「どのように生き、どのように死を迎えるか」を個人が主体的に考える必要があるという視点から書かれている。「老化は病気であり治療できる」というデビッド・シンクレアの提案した概念がアメリカでは常識化し、多額の研究投資も行われている。
Eさん
◆『キッチンの歴史 料理道具が変えた人類の食文化』ビー・ウィルソン(河出書房新社) 食の歴史を「調理道具の進化」という視点から紐解いた一冊。著者は政治思想史の研究者でありながら、食文化に関する執筆でも高く評価されてきたフードライターで、豊富な知識とユーモアに富んだ筆致で、古今東西の料理道具の由来や変遷を紹介しています。
本書では、包丁や鍋、オーブンなどの身近な道具はもちろん、ピーラーや炊飯器といった現代的な器具についても詳しく論じられ、単なる調理道具の説明を超えて、それがいかに人々の食習慣や暮らしを変えてきたかが語られます。たとえば電気炊飯器の登場が、東アジアの家庭における夕食の支度の負担をいかに軽減したか、また西アジアや南アジアでは長粒米の性質上、炊飯器が広く普及しなかった理由など、具体的な地域差と文化背景の考察がとても興味深い内容です。
また、ピーラー(皮むき器)の進化においては、刃の切れ味だけでなく「握りやすさ」といった人間工学的な発想が重要であることが語られ、「道具とは、使う人の手と心にどう寄り添うか」が問われていることに気づかされます。
紹介者からは、調理道具の研究に関心を持つ立場から「専門書とは違い、広い読者層に向けて書かれているが、内容は実に深く、自分の生活を見つめ直すきっかけにもなる」との感想がありました。時間のあるときに少しずつ読むのにも適しており、料理をする人はもちろん、道具に興味のある方にもおすすめできるユニークな食文化論です。
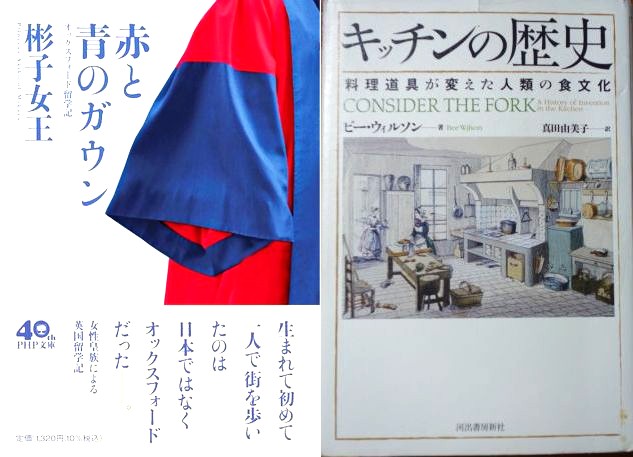
Fさん
◆『春の戴冠 全4巻』 辻 邦生(中公文庫) この本を読むことになった「きっかけ」は2025年3月29日@丸紅ギャラリーで『ボッティチェリ「美しきシモネッタ」特別公開展』を観てから・・・ というお話や、高校時代に触れた辻邦生の印象と今回読み始めての途中の感想を話していただいた。今年は辻邦生生誕100年、プレカレ年代に根強い人気があることが討論の中で分かった。
Gさん
◆『賢治と「星」を見る』渡部潤一NHK出版(2023/7) 宮沢賢治の作品は全てではないが多くを読んでいる(複数回読んだものの多い)。また、賢治が当時として最先端の天文学・気象学・農学・土壌学の造詣があったことも知っていた。一方、賢治の人生については、フィクションではあるものの直木賞作品、門井慶喜『銀河鉄道の父』を昨年読んで初めて知った程度である。今回紹介する書籍は、著名な天文学者で、且つ、言葉悪いが賢治の偏愛者である著者が、天体を主な対象とし、それに係る作品(及び作品の一部)と賢治の人生・人となりを関連付けて考察し読者に紹介するものである。
作品の素晴らしさは、その背景を知らずとも十分味わえると思う。再度、作品を読み直してみるのもよいだろう。賢治作品をより深く味わいたくなるような、新たな視点が得られる。
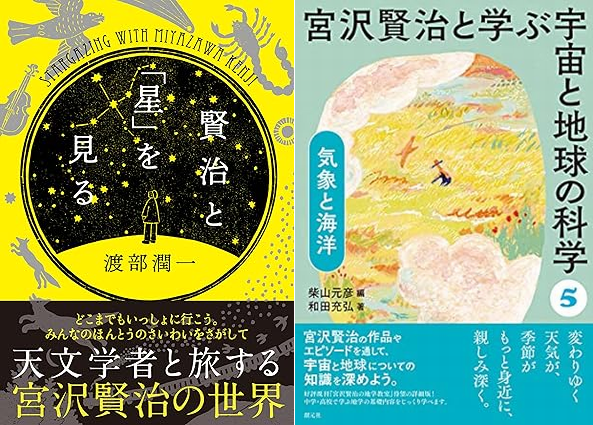
Hさん
◆『君は隅田川に消えたのか』駒村吉重(講談社) 若き版画家・藤牧義夫の謎の失踪と、残された作品をめぐる真実に迫るノンフィクション。版画界の裏面史も見えてくる興味深い一冊。近年評価の上がっている藤牧義夫の作品の紹介もしていただいた。
Iさん
◆『赤と青のガウン』彬子女王(PHP文庫) 1981年生まれ、故寛仁親王(ともひとしんのう)の第一子。学習院大学卒業後、イギリスオックスフォード大学マートン・カレッジに留学、6年間の留学生活を軽妙な筆致で綴ったエッセイ。章タイトルに四字熟語を配するなど、知性と品のある構成で、チュートリアルの厳しさもリアルに描かれている。
Jさん
◆『イラク水滸伝』高野秀行(文藝春秋) イラク南東部の湿地帯を旅した異色のルポ。メソポタミア文明の痕跡と人々の暮らしに触れ、自由な取材の旅が展開される。
◆『琉球王国の南海貿易』高良倉吉 編(吉川弘文館) 中継貿易で栄えた琉球王国の実態を多角的に検証する学術書。朝貢船や南海貿易、大航海の航路や交易の相手国まで詳しく記され、歴史好きには読み応えのある一冊。
次回の読書会
開催日: 7月18日(金)13:00~
第一部 テーマ本:
•『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい』佐藤拓己(光文社、2025)
•『鳥類学者 無謀にも恐竜を語る』川上和人(新潮社、2018)
第二部(14:40~15:40):
出席者によるおすすめ本の紹介です。どうぞお楽しみに!
(文責 正田、小原)


コメント
コメント一覧 (2件)
拙著をお取り上げ頂きありがとうございます。
週刊ダイヤモンド書評欄で推薦されており、読ませて頂きました。
第7章の最後で述べられている、人間の脳と生成AIやLLMはその無数にある世界シュミレーターのたった二つのリアライゼーションに過ぎないと思うのが、もっとも妥当な見解である可能性が高い、との内容で知能について、少し理解出来たと感じました。