開催日時: 2025年8月29日(金)13:00~15:00
開催場所: 八雲倶楽部
出席者: 9名
【読書会報告①】
堤未果『デジタル・ファシズム』(NHK出版新書, 2021)。刊行から4年、2025年の今読み返すと、当時は“警鐘”だった指摘の多くが半ば常識化していることにまず驚かされます。著者は、デジタル庁の権限集中と人材登用の不透明さ、外資クラウド依存やZoom公用のリスク、キャッシュレスに潜む「預金保護の外側」問題、行動履歴の丸裸化を丹念に検証。中国の社会信用、韓国の過剰与信と破綻の連鎖を引き、便利の陰に潜む「統治と市場の結託」を問います。他方、台湾のオードリー・タンは分散設計と透明性で“テクノロジーで民主主義を深める”好例として提示。教育ではGIGAスクール端末と外国OS依存がデータ主権の論点を直撃し、教科書なき授業の到来を展望します。討議は、日本史教育の現代史の薄さ、行政調達と安全保障、○○Pay口座の破綻時リスクまで拡散。「集めない・任せきらない・確かめる」を“ポケット憲法”に、が本日の合意。結論は実務的です。スマホ一台が身分証+財布+行動記録なら、手放すべきでないのは警戒心、やってはいけないのは安易なクリック。指先一つが主権やリスクの入口にも出口にもなる——その緊張感を、ユーモアと一緒に習慣化したいところです。

【読書会報告②】
保谷彰彦『タンポポハンドブック』(文一総合出版, 2017)。花・総苞・蕾・冠毛・種子・葉を軸に、日本の約30分類群を同定へ導く“検索表”付きの携帯図鑑。低地から高山帯までの地域変異を俯瞰し、在来・外来・雑種の識別、倍数性や雑種形成も要点イラストで腑に落ちます。紹介者はアースウォッチのバックヤード調査に参加し、相模原市立博物館で花粉プレパラート作りに挑戦。偶然手に取った愛知の小学5年生の標本が、希少な在来「トウカイタンポポ」と判明し、秋山学芸員・倉田教授の確認で場がどよめく一幕も。雑種優勢が進む今だからこそ、「名付けること=多様性を守る最初の一歩」を実感しました。討議は、総苞外片の反り返りの見分け方、ボランティア参加の敷居、食用利用の可否、そして“なぜ在来が30も分化したのか”という進化史まで縦横無尽。来春は本片手に“野の研究者”ごっこを——が決起表明。合言葉は「迷ったら総苞、詰まったら分布、写真は真正面」。SNSの“映え角度”ではなく、科学の“見え角度”で野原へ。
【読書会報告③】
孫崎享『私とスパイの物語』(ワニブックス, 2025)と、Bee Wilson『キッチンの歴史』(河出書房新社)。一見無関係な二冊が「道具と段取り」で気持ちよく結びつきました。前者は駐在の現場からMI6・CIA・モサド・KGBの作法を回想し、映画的伝説と実務の落差を可視化。華麗な潜入より、地味な収集・分析・関係構築が要。現代は“人”のスパイが減り、監視・傍受などハイテク主戦場へ移行し、大使館業務との境界が論点に。オードリー・ヘプバーンやヘミングウェイの「噂」を検証しつつ、価値観の越境こそ諜報の本質だと説きます。後者は鍋・ナイフ・火・計量・「挽く」といった台所道具から文明を読み解く快著。火は料理を可能にし、共同体をつくり、脳を育てた——という人類史の視点、「砕く」の文化史は効率と身体性のトレードオフを問います。討議は「買うほどでは? でも図書館でぜひ」と現実的に落ち着きつつ、諜報と公館情報の違い、家庭の火は誰のものかへ。締めの一句。「機密は弱火で、噂は粗挽き。煮詰める前に味見を」。道具に振り回されず、段取りで世界を解く——そんな読後感でした。
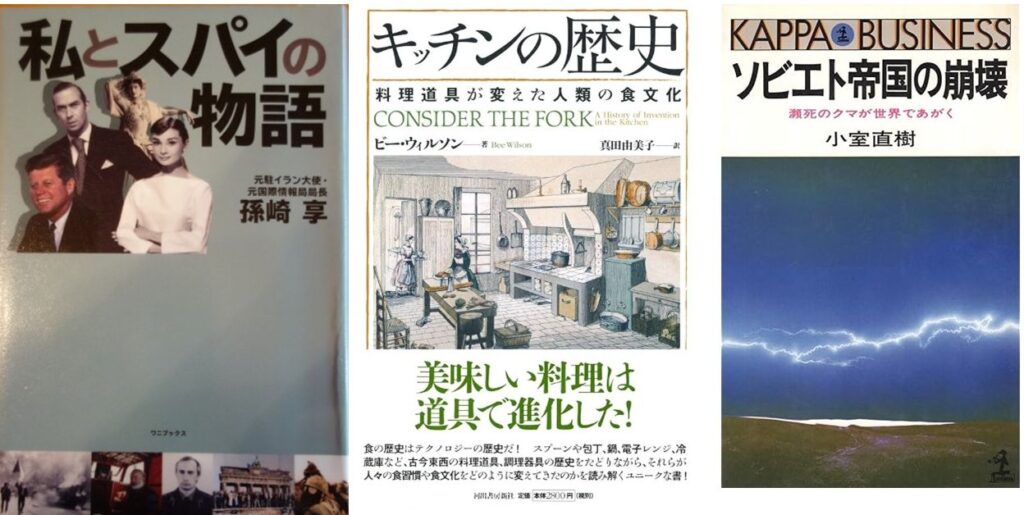
【読書会報告④】
小室直樹『ソビエト帝国の崩壊―瀕死のクマが世界であがく』(光文社未来ライブラリー, 復刊)。1980年のデビュー作で「内部崩壊は不可避」と断じた論旨は、①無階級の建前の陰で特権層が富と権力を独占、②貨幣より“コネと権力”が通貨化した闇経済、③党・軍・軍需の自己目的化、④近代的エートスの欠如、⑤スターリン批判後の急性アノミー、⑥軍の虚像化——という冷徹な積み木で構築。張り子の熊の比喩は軍事抑止の心理作用まで射程に入れます。約10年後に崩壊は史実となりましたが、討議は現在形へ。「なぜロシアは復活し得たのか」「資源・国家資本主義・情報空間の統合はどこまで持続するのか」。教訓は辛口ながら明快です。制度は人の意識とインセンティブの鏡で、鏡が曇れば現実は歪む。権力と市場の相互監視が消えれば、再び“熊”は迷走する。歴史書としてだけでなく、危機管理のハンドブックとして傍らに置きたい一冊。ページを閉じても、私たちの中の“小さな張り子”を壊す作業は続きます。
【読書会報告⑤】
今回は二本柱——「大河×経済史の再評価」と「科学でひらく物語」。まず村木嵐『まいまいつぶろ』(2023)『またうど』(2024)。嘲られがちな九代将軍・家重を大岡忠光との信頼で描き直し、若き田沼意次が現場感たっぷりに立ち上がる。続編では“またうど=全う人”の意次・意知が主役。専売・流通・為替、相良藩での実務まで、机上ではなく制度設計と合意形成の汗がにじみ、賄賂政治のレッテルを越えて「簿記と政策が江戸を動かした」手触りが戻ります。
一方、伊予原新。神戸大→東大院・地球惑星で理博、富山大助教を経て作家へ。2025年『藍を継ぐ海』で第172回直木賞。国立科学博物館の普及講演で知った「はやぶさ2」の高校アイデア採用と、そのNHKドラマ『宙わたる宇宙』の原作が伊予原——という“入口”から作者に出会いました。『青ノ果テ—花巻農芸高校地学部の夏』は来月テーマの宮沢賢治に直結。『銀河鉄道の夜』の地理モデルを追う縦走劇に、イーハトーブの射程、第4稿と旧稿の差への考察が織り込まれ、恩田陸『夜のピクニック』の高揚感に理科部のロマンと検証が混ざります。短編集『八月の銀の雪』は、科学がささやかな希望へ橋渡しする五篇——表題作=地球内部構造/「海へ還る日」鯨偶蹄目/「アルノーと檸檬」渡りと鳩の帰巣/「玻璃を拾う」珪藻/「十万年の西風」原発事故と風船爆弾。安易なハッピーエンドに逃げず、出会いと思索が視界を1度だけ明るくする“科学の灯”が魅力です。
討議の結論はシンプル。江戸の改革も理科室の発見も、世界を動かすのは「段取り×検証」。帳簿と星図、双方の数字が物語を押す。次回は賢治特集。家重とジョバンニが同じ卓に座ったら——請求書は田沼、時刻表はカムパネルラ。こんな組み合わせこそ読書会の楽しみです。
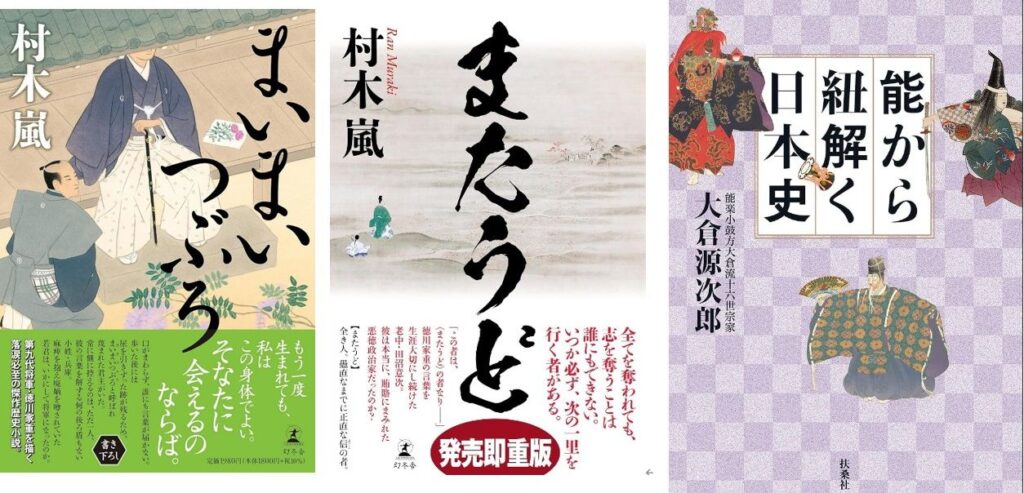
【読書会報告⑥】
大倉源次郎『能から紐解く日本史』(2021)。小鼓方大倉流十六世宗家にして人間国宝の語り口は、難解に見える能を一気に“近所の歴史”へ引き寄せます。シテ・ワキ・ツレ・子・狂言・囃子の諸流派、そして『国栖』『夕顔』『白髭』『大江山』『花筐』『翁』『梅』『養老』『石橋』などの演目を通路に、舞台裏の古代史を会話体で案内。白眉は修験道の影響論。役行者に始まる山岳信仰、神仏習合と“権現”概念が能の根に流れる——という“演者の肌感覚”の仮説が刺激的です。終盤、本名「大倉源次郎秦宗治」が明かされ、世阿弥の名乗り「秦元清」や弓月君伝承、『新撰姓氏録』とつながる秦氏の広がりへ視野が開けるのも痛快。討議は、近年の遺伝学や古墳期の渡来影響、芸能と渡来系氏族の関係へと寄り道しつつ、「奈良時代人口約500万人のうち秦氏17万人説」「渡来人はいつ・どう来たのか」まで議論は尽きず。最後は、舞台の松と橋掛かりの向こうに山霊と古代の越境者が立つのが見える——そんな余韻を残す一冊でした。
【読書会報告⑦】
葉室麟『霖雨』と植松三十里『侍たちの沃野』。前者は日田の儒学者・広瀬淡窓と、家を継ぎ地域を支えた弟・久兵衛の兄弟譚。代官の干渉に翻弄されながらも、私塾・咸宜園に全国の若者が集う光景は、教育が“雨のように人を育てる”ことの具体です。とりわけ久兵衛の「霖雨蒼生」の志——長雨のように民草を潤す姿勢——に胸を打たれます。後者は明治10年、猪苗代湖の水を郡山へ引く安積疏水の国家プロジェクト。大久保利通の構想を中條政恒・南一郎平らが蘭人技師と共に実装し、暗殺や内紛、地形と予算の壁を越える群像劇。二冊を重ねると見えてくるのは、肩書ではなく“役目に見合う責任”で公共を増やすノブレス・オブリージュ。雨で人心を耕し、水路で未来を広げる——そんな比喩が討議を潤しました。宿題は現代の私たちへ。「地域に一筋の疏水を」「身の丈の霖雨を」。大事業でなくてよい、今日の一滴が明日の沃野をつくる、と背を押される読後感です。
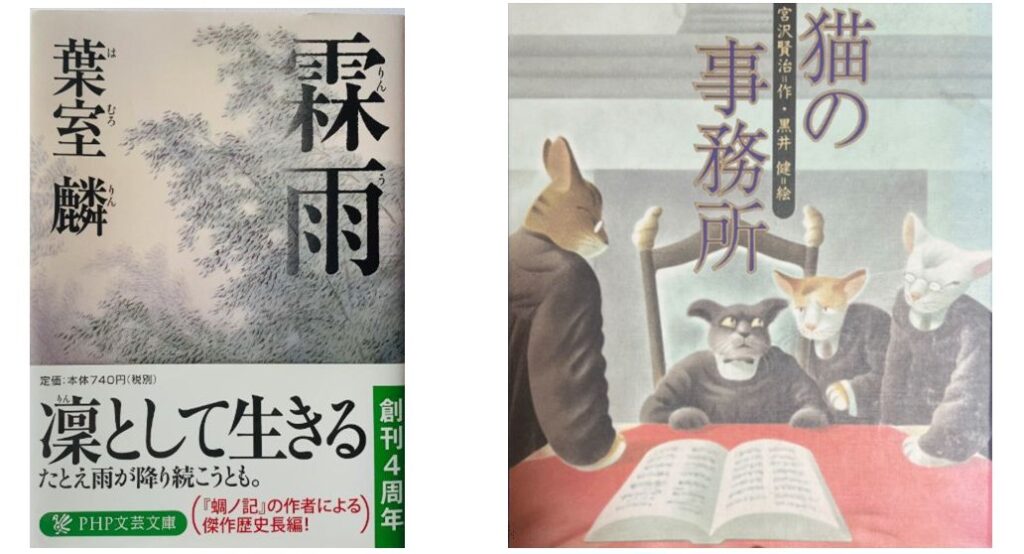
【読書会報告⑧】
宮沢賢治『オッペルと象』『猫の事務所』。前者は、巨体の象と群衆心理のうねりで、世論の“さざ波”が生む暴力を寓話化。「周りに簡単に流されるな」という警告は、拡散速度が速すぎる現代にほどよく刺さります。後者は、書式と序列に縛られた猫役所の滑稽が、笑いながら胃に重く残る一編。末尾の「僕は半分獅子に同感です」が秀逸で、半分にとどめることで残り半分の解決を読者に委ねる“対話の余白”が生まれます。討議は、学校・職場・地域の“あるある”へ波及し、「正義の吠え方」「少数派の救い方」「書式の呪いからの脱出法」まで具体論に。結論は柔らかな実践です。①すぐ怒らない ②すぐ群れない ③すぐ回さない(とりあえずの拡散は控える)。そして次回は賢治特集へ。銀河鉄道で行くもよし、『注文の多い料理店』で腹ごしらえもよし。賢治は100年後の私たちに「半分」を返してきます。残り半分は、私たちの番です。
次回
9月26日(金) 13時より 渋谷八雲クラブ
宮澤賢治の作品のどれか数冊(何でも可)を読んで皆で賢治について語り合いたい思います。
本の紹介は任意とします
(文責 正田、小原)


コメント