開催日時:2025年3月28日(金)13:00~15:10
開催場所:八雲クラブ
出席者:10名
今回は初めての出席者2名を含め10名の出席で開催されました。紹介された本は全部で8冊、前回同様非常に広範囲に渉るテーマで、各人より活発な議論が展開されました。
今回もお互いを知るために本の紹介に終始しましたが、今後は皆で読む本を1冊決め、それを全員が読み込んで議論をすることも検討することになりました。
〈紹介された本〉
A氏:『博士の愛した数式』小川洋子 2003年、新潮社
【あらすじ】
シングルマザーの “私(28歳)”が家政婦紹介で派遣された先は、80分しか記憶が持たない高齢(64歳)の元数学者「博士」の家だった。こよなく数学(数論)を愛するが、他に全く興味を示さない博士に、”私” は困惑する。ある日、”私” に10歳の息子がいることを知った博士は、幼い子供が独りで母親の帰りを待っている寂しさを慮って、次の日からは息子を連れてくるように言う。次の日連れてきた ”私” の息子の頭を撫でて、博士は彼を “√” と名付け、3人のぎこちない日々が始まる。
博士の記憶は80分しか続かないが、”私” とその息子は博士の純粋な温かさに触れて、やがて心を通わせていく。博士の真剣に生きる純粋な気持ちに、日々驚き・歓び、心豊かとなり、生活は満ちたものに変わってゆく。しかし、心の触れ合いは有るが、記憶が80分しか持たないこと、年齢の差が大きいという非生活感でその幸福感は温かいが、切なさが同居している。
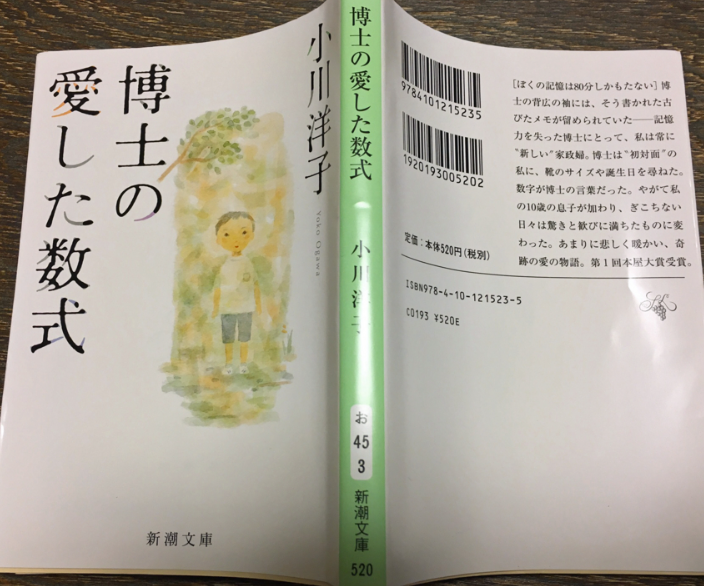
B氏:『マハン海上権力史論』アルフレッド・T・マハン(米)1890年 原題:The Influence of Sea Power upon History,1660-1783 Alferd Thayer Mahan 1840〜1914 年
アメリカ海軍の軍人、歴史家、軍事評論家 海軍兵学校卒業後、南北戦争に従軍。1886-89年および92-93年、海軍大学校校長。 1902 年アメリカ歴史学会会長。1906年少将で退役。地政学の祖といわれている。 その頃(1890年=明治23年)の日本は・・・ 府県制・群制公布がされる、第1回帝国議会開会、絹糸生産量が輸入量を超える、 大津事件(ロシア皇太子襲撃負傷事件)(1891年)など
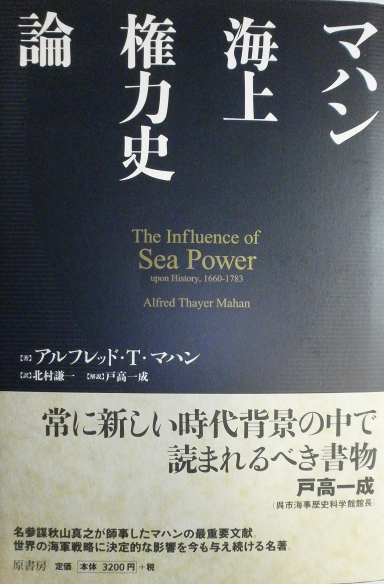
C氏:『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい』佐藤拓己(2025)光文社
【紹介主旨】
シニア世代(60~65歳以上)が子供の頃は恐竜は爬虫類の一部(先祖)に考えられ、また、肉食恐竜(ティラノサウルス等)は映画「ゴジラ」のように直立に近い前傾姿勢で書かれることが多かった。その後、映画「ジュラシックパーク」やNHKの科学ドキュメンタリーで
○恐竜=獣脚類と鳥類は同じ系統である(鳥は恐竜の生き残りから派生)
○恐竜には鳥と同じく羽毛があり骨に気嚢を持つ物がいた
○肉食系恐竜は頭部と尾部がほぼ水平に近い前傾姿勢であった
ということは今でも広く人口に膾炙している。しかし、鳥の前駆であった恐竜=獣脚類、及び鳥類の類い希な運動能力とそれを実現する生態機構を知ることがなく、本書により理解が大いに進んだ。
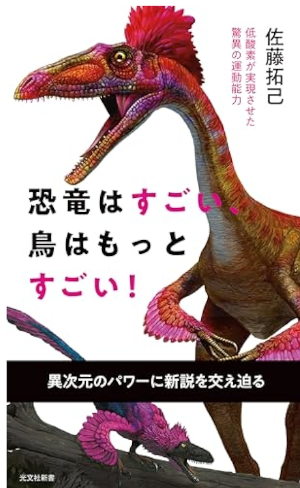
D氏:『歩く マジで人生が変わる習慣』 作者:池田光史 経済ジャーナリスト、NewsPicks編集長
1 脳のこと
2 身体のこと
3 街のこと
4 足のこと
5 靴のこと
6 自然のこと
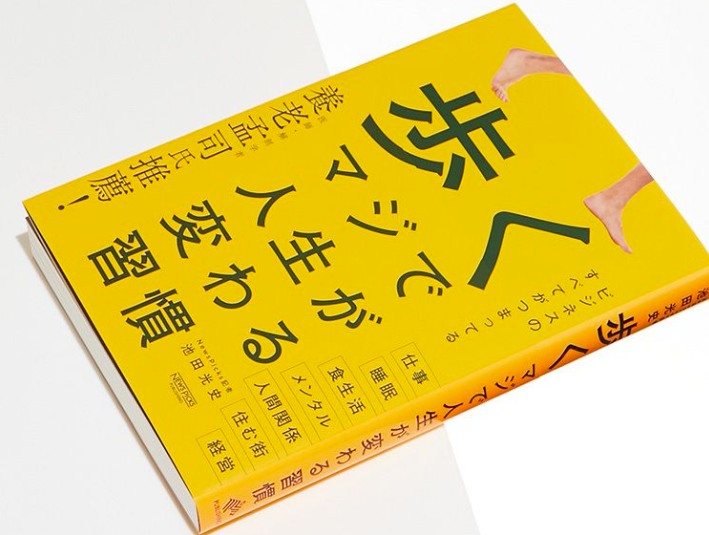
E氏:『老後ひとり難民』沢村香苗 幻冬舎新書
準備不足な“おひとりさま”の悲惨な末路。世はおひとりさまブームで、独身人口は増え続けるけるばかり。だが、そのまま老後を迎えて本当に大丈夫だろうか? 配偶者や子どもなどの“身元保証人”がいない高齢者は、入院だけでなく、施設への入居を断られることも多い。トラブルを回避する方法と、どうすれば安心して老後を送れるのかについて書いている。
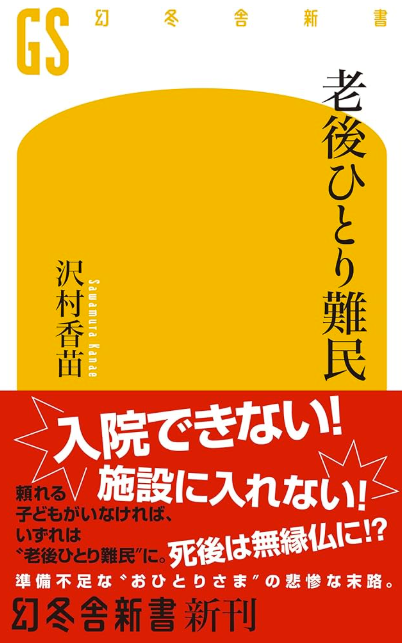
F氏:『家事は大変って気づきましたか?』阿古真理 亜紀書房
■第1章 家事とお金のままならない関係
1.家事のムーブメントを加速させた『逃げ恥』
2.家事代行サービスという方法
3.「名前のない家事」とは?
4.家事をやった気になっていばる夫
5.本当に養っているのは誰?
6.「マッチョな夫=羊飼い」説
7.夫婦のパートナーシップ
8.ケアとクリエイティビティ
■第2章「家事=妻の労働」になったのは昭和時代だった
1.手料理には愛情が必要ですか?
2.女性たちを縛る「家事=愛情表現」という思い込み
3.根深く残る母性愛神話
4.主婦論争が示したもの
5.女中が必要だった時代
6.農家の女性たちの生活改善運動
■第3章 昭和・平成・令和 食事づくりの現場で
1.「ていねいな暮らし」への愛憎
2.男女の役割分担から脱出する
3.一汁一菜ブームとは何だったのか?
4.時短料理はなぜブームになったのか?
5.巣ごもり生活でわかった、自炊力という武器
■第4章 家事を「大変!」にするのは何?
1.カリスマたちが教える、片づけが秘める魔力
2.お手入れしやすい住まいとは?
3.実は高度な家事、買いものと献立
4.「ひと手間」がわずらわしいのはなぜ?
5.料理が苦痛になるのはなぜ?
6.家事は一朝一夕には覚えられない
7.グチを受け止めてくれる人はいますか?
8.家族とライフスタイル
■第5章 シェアするのは難しい?
1.頼りにならない父親たち
2.育児に〝当事者意識〞を持っていますか?
3.大掃除は、家事シェアを日常化させるチャンス!
4.子どもに料理を教えると……
5.平等な家事シェアは可能か?
6.平等なシェアがゴールなのか?
7.どうする? 家計管理
■第6章 ケアと資本主義
1.『モモ』が描いたケア
2.主婦たちの虚無感
3.ケアとは何か?
4.ケアを閉じ込めた家父長制
5.資本主義のたくらみ
6.私たちにできること

G氏:『ワイマル共和国~ヒトラーを出現させたもの』(林健太郎)1963 中公新書
○著者:林健太郎(1913~2004)東大教授西洋史学専攻 第20代東大総長
〇本書目的:ワイマル共和国は当時最も民主的な憲法であるワイマル憲法を制定したにも
拘わらず、15年足らずでナチスに合法的に乗っ取られたのは何故か
〇ワイマル共和国失敗の要因
・様々な分断の存在=南北、宗教、民族、多くの政党
・対外要因:①ヴェルサイユ条約による厳しい賠償 ②世界恐慌
・内的要因:①国制上の欠陥=大統領の権限 ②国会の機能喪失=政党の未成熟
・国民の、苦境から現状打破の要求
・ナチスの戦略=合法的な手段で政権獲得を目指し、民主主義を終わらせる
元々の支持基盤はプロテスタント中産階級。資本家を味方にし、国
防烏軍を敵にしない=外国・外来思想、異人種の排撃
それが国民の異常な人気を得、国防軍と官僚が支持
〇結論:ドイツ人は目前の苦境に追われて社会と人間の存立のために最も重要なものが何
であるかを認識することを忘れた
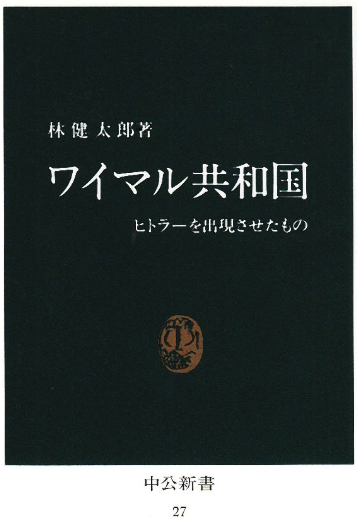
H氏:『なぜ悪人が上に立つのか』ロバート・M・サポルスキー東洋経済新聞社
人間の社会における権力構造と倫理の関係を、神経科学や行動生物学の視点から分析した書籍である。本書は、権力を持つ人々がどのようにして道徳的に逸脱しやすくなるのかを、脳のメカニズムや進化的背景をもとに解明している。
サポルスキーは、権力を持つと人間の脳内でドーパミンが増加し、報酬を求める傾向が強まることを指摘する。これは、倫理的な判断よりも自己利益を優先させる行動につながりやすい。また、権力者は共感を司る脳の部位(前頭前野やミラーニューロンの活動)が低下し、他者の苦しみに鈍感になることが研究で示されている。
さらに、権力を持つことで社会的階層が意識されるようになり、強者は自らの地位を正当化しやすくなる。これにより、特権を享受する者が倫理的な規範を無視する傾向が強まる。歴史的にも、独裁者や企業のトップが倫理的な逸脱を犯す例は多く、これは単なる個人の資質ではなく、権力が持つ構造的な影響によるものだと著者は論じる。
一方で、サポルスキーは「権力は必ずしも腐敗を生むわけではない」とも述べる。透明性の高い制度や強い倫理観を持つリーダーがいる場合、権力がより良い方向に働く可能性もある。しかし、一般的には権力が集中すると道徳的な逸脱が起こりやすいため、チェック機能を強化し、権力の分散を図ることが重要であると説く。
本書は、単なる道徳論ではなく、脳科学や行動生物学の研究を基に、なぜ権力が人を変えるのかを科学的に説明している点が特徴的である。サポルスキーは、読者に対し、権力の本質を理解し、それをコントロールする仕組みを社会に組み込む必要性を強く訴えている。
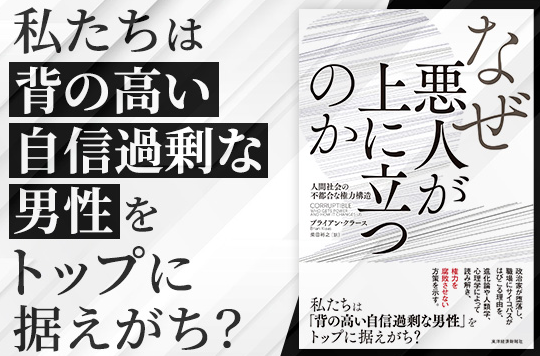
次回読書会のお知らせ
開催日時:2025年4月25日(金)13:00~ 八雲クラブ
5月23日(金)13:00~ 八雲クラブ
内容:今回と同様に、各自が紹介したい本をA4用紙1枚にまとめ、プレゼンを行う予定です。紹介したい本がある方は、ご準備をお願いします。
(文責 1期生 正田、小原)


コメント