開催日 : 2025年7月24日(木曜日)
開催場所: オンライン
出席者 : 荻野、関、増山、森本、宮嶋、深田、鈴木[入会順、敬称略]
発表者 : 増山 憲司
【発表概要】
第33代推古天皇と聖徳太子の初回(第24回)は、初となる(女帝+摂政)という政治体制が実現した時代背景や経緯について探ってみました。
次に、前回(第31回)は、太子の著名な功績とされている「冠位十二階」と「十七条の憲法」の制定について、これらの新たな施策が生まれた時代背景とそれらの狙いについて調べました。
そして、3回目となる今回の発表では、その後の太子の活動に焦点を当て、仏教への傾注から最期まで、そして有力豪族蘇我馬子と推古天皇の最期についても調べてみました。
太子は、冠位十二階および十七条の憲法を制定した後は、政治面における顕著な実績の記録はありません。その理由としては、太子のその後の注力分野が政治から仏教そのものに移っていったことが考えられます。仏教への傾注については、十七条の憲法の第一条「和を以て貴しと為し、忤う無きを宗と為よ」に続く、第二条に「篤く三宝を敬え」という条文を配置したことからも推察できます。 即ち、「篤く三宝を敬え」が示すとおり、あらゆる生き物およびすべての国の究極の拠りどころとして「大乗仏教」を位置づけ、太子自ら真髄する姿勢を示したものと考えられます。 さらに、太子は、601年に建設を開始した斑鳩宮の完成後、605年に斑鳩宮へ移転され、その後607年、斑鳩に法隆寺を建立されました。こうして、太子が斑鳩の地にて仏教を極める環境が整ったと推察されます。

斑鳩宮と法隆寺
太子の具体的な仏教に関する活動としては、天皇や蘇我馬子らの主要人物を対象に勝鬘経(しょうまんきょう)や法華経の講義をしたり、伝来した大乗仏教の理解を深め、その布教を目指して三経義疏(さんきょうぎしょ)を執筆したことが記されています。 三経義疏とは、勝鬘経、維摩経(ゆいまきょう)、法華経の解説書であり、勝鬘経義疏を611年に、維摩経義疏を613年に、法華義疏を615年に完成させたとされています。 筆者は、これまで仏教に関する詳しい知識を持ち合わせていなかったので、今回は三経それぞれの構成や内容について若干なりとも理解を深めようと試みました。本報告では、三経それぞれの概要の記載は割愛しますが、「衆生」、「声聞」、「縁覚」、「涅槃」、「菩薩」、「一乗」などの仏教用語を含め、多少ながらも概略のイメージは理解できたと感じています。
聖徳太子は、当時斑鳩周辺で流行していたとみられる感染症(天然痘と推定されている)に感染し、622年に49歳で薨去されました。太子の墓は、大阪府南河内郡太子町の叡福寺にある磯長墓とされており、母の穴穂部間人皇女と妃の膳部菩岐々美郎女を合葬した三骨一廟と伝えられています。
593年の推古朝発足以降、推古天皇、聖徳太子、蘇我馬子の三者が政権の中枢を構成し、運営していたとされていますが、聖徳太子が薨去された後は、蘇我氏の専横(他の意向を無視して好き勝手に振舞うこと)が拡張し、やがて皇室との対立を招き、乙巳の変から大化の改新に至る土壌が形成されていったと考えられます。 蘇我馬子は、626年に76歳にて死去し、桃原墓(明日香村の石舞台古墳だとする説が有力)に葬られ、馬子の公職については、子の蝦夷に引き継がれました。
馬子の死去から2年後、628年に推古天皇は75歳で崩御され、若年で亡くなった子の竹田皇子との合葬陵墓として磯長山田陵に葬られました。 天皇は生前に後継者を指名されなかったため、このことが後の皇位継承争い(田村皇子か、山背大兄王か)に繋がっていきました。
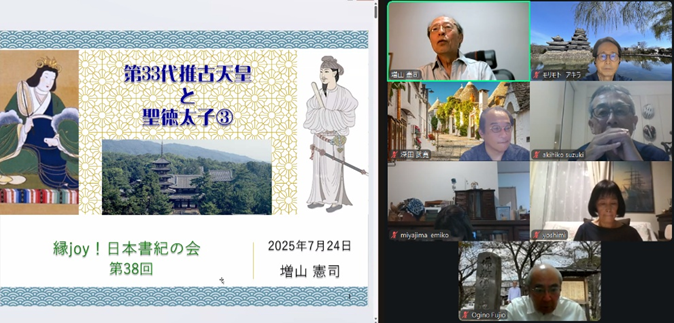
第38回オンライン定例会の様子
(記)増山憲司

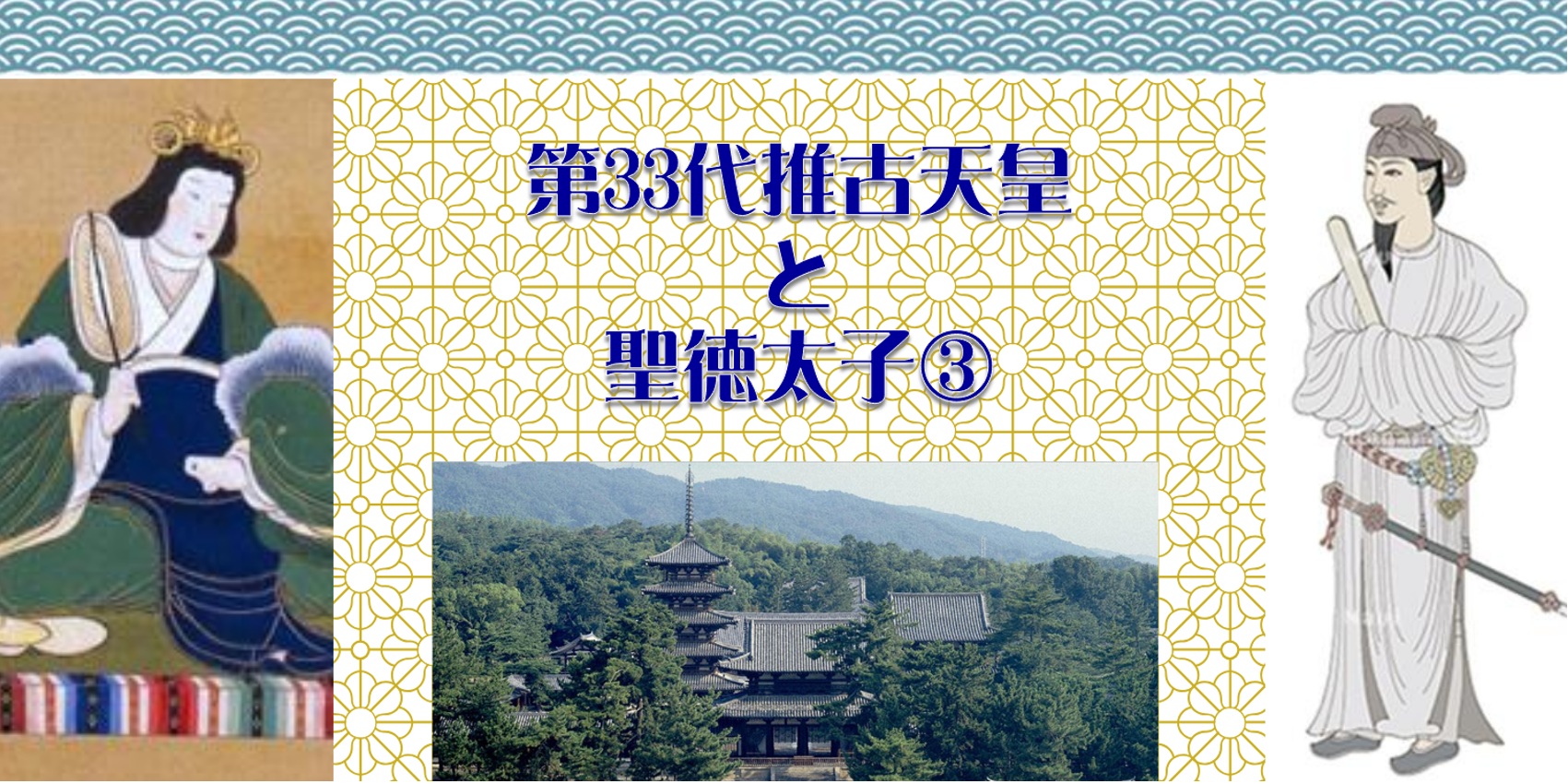
コメント