開催日時: 2025年7月18日(金)13:00~15:30
開催場所: 八雲倶楽部
出席者: 7名
読書会報告:一部
今回は「鳥と恐竜でこんなに盛り上がるとは!」という驚きの読書会でした。
テーマは、なんと“恐竜と鳥”。扱ったのは以下の二冊です。
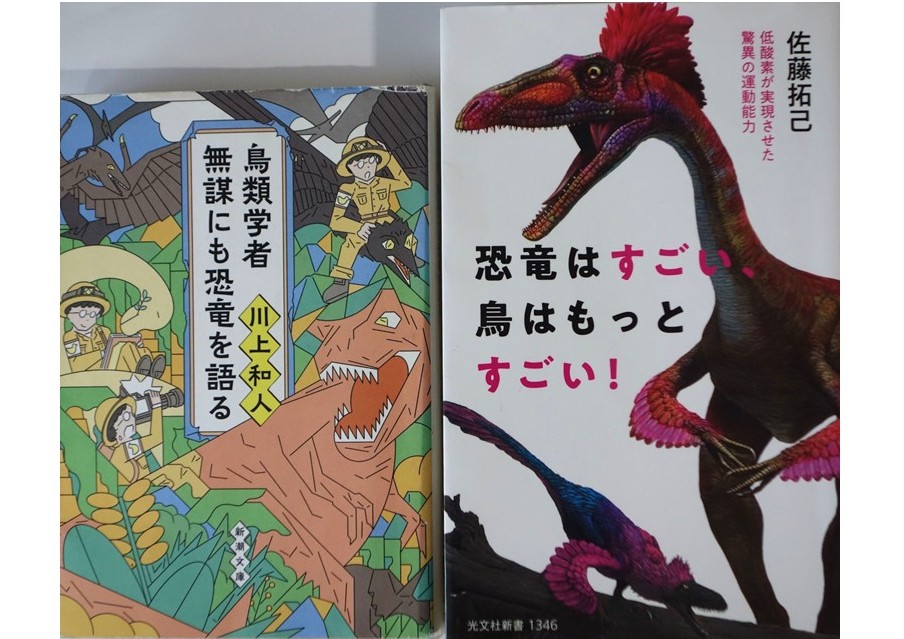
•『鳥類学者 無謀にも恐竜を語る』川上和人 著
•『恐竜はすごい、鳥はもっとすごい!』 佐藤拓己 著
この2冊、タイトルだけで「これは面白そうだぞ…」と期待させてくれますが、読んでみると期待以上。恐竜好きにも、鳥がスズメとカラスぐらいしか思いつかない人にも、まるっと楽しめる内容でした。 会の冒頭では紹介者のAさんが、いつもながらコンパクトかつ要点を押さえたブリーフィングをしてくださいました。
川上さんの本については「生物や恐竜に特別な関心がなくても、思わず引き込まれるユーモアと知性にあふれた本」とのこと。著者が別の本のあとがきで「学者は科学をおもしろく伝える義務がある」と語っていたそうですが、その信念が見事に体現された一冊でした。
佐藤さんの本の方はというと、タイトルにあるように「恐竜もすごいけど、鳥はもっとすごい!」。実際に読んでみると、鳥類の驚異的な運動能力から、地質時代における生物たちの浮き沈みの壮大な物語までを網羅し、人類がどれほど“特別じゃない”生き物かを思い知らされます。
参加者の感想で共通していたのは、ただひと言――「とにかく、面白かった!」
そこから話題は広がり、あっちへ飛び、こっちへ飛び…いや、まるで渡り鳥のように(?)大きく展開していきました。
• 進化ってやっぱり不思議!
• 生き残るか滅びるかを決めるものって何?
• 地球の歴史と人類の時間感覚って全然違うね…
• 恐竜があれだけ栄えていたのにあっさり絶滅。人類も案外早く終わるかも?
• 最後に生き残るのは、やっぱり鳥か!?
そして「恐竜の絶滅=隕石」という小学生レベルの記憶が、PT境界やKT境界といった大絶滅イベントの話にアップデートされ、さらにその後の生態系の変化まで整理できて、まさに“頭の中の恐竜博物館”が刷新されたような爽快感!
「高度8000m、酸素濃度7%、気温マイナス30℃、風速30mという悪条件の中、アネハヅルがヒマラヤを飛び越える話」には、みんなで「ええーっ!?」と驚嘆の声。これはもう、鳥を見かけたら思わず敬礼してしまいそう。
そして何より印象的だったのは、「鳥が恐竜の子孫」という事実に、今さらながらに感動したという声も多く…。「始祖鳥って習ったけど、それが本当に恐竜から来てたのね」と再発見の連続でした。鳥類学者が恐竜を語る…これ、全然“無謀”じゃありません!
「人間が“頭脳”で進化のトップに立ったと思っている間に、鳥たちは空を飛び、地球を縦横無尽に移動し、氷河期も宇宙からの衝突も生き延びてきました。もしかしたら“賢い”よりも“しぶとい”ほうが、生き残りには大事なのかもしれません。」
________________________________________
今回の読書会は、「鳥と恐竜」というテーマを通じて、科学のおもしろさ、地球の長い歴史、そして人類のこれからにまで思いを馳せる、濃密で楽しいひとときとなりました。
読書会報告:二部 自由紹介本コーナー
ここからは参加者が「今おすすめしたい!」と選んだ本を紹介する自由コーナーです。それぞれの興味関心がにじみ出ていて、バラエティ豊か。歴史から哲学、投資、進化論にセミの死にざま(!)まで、知的な散歩道を自由気ままに歩くような時間となりました。
Bさんの本棚から:晩年の知的冒険は鎌倉から
今回の紹介テーマは『吾妻鏡』とその周辺本。鎌倉時代に興味があるというBさんは、自宅の本棚で眠っていた関連書を再読しながら「人生後半、気ままに歴史研究でもしてみようか」と静かに野望を燃やしているご様子。紹介されたのは以下の3冊+1。
1.『吾妻鏡』西田友広 編(角川ソフィア文庫)
武家政権最初の記録とされる基本史料。鎌倉時代を知るには欠かせない一冊です。
2.『吾妻鏡 鎌倉幕府「正史」の虚実』藪本勝治(中公新書)
正史とされる『吾妻鏡』に潜む意図や欠落に光を当てた解説本。歴史書を読む「目の付け所」が変わります。
3.『吾妻鏡必携』関幸彦・野口実 編(吉川弘文館)
手元に置いておきたい、鎌倉時代研究の“道具箱”的一冊。
『吾妻鏡』には、3年間の空白期間(頼朝死去前後など)や、北条家寄りの視点といったバイアスもあり、鵜呑みにはできませんが、それでも鎌倉を知る上での“とっかかり”としては極めて重要。Bさんの目は、もはや現代よりも中世を見つめているようでした。
Cさんのおすすめ:経済を読む、未来を考える
経済の視点から日本の行方を見つめたCさんは、5年前の提言書ながら、今なお示唆に富むと語る2冊と、話題の投資本を紹介。
1.『日本企業の勝算』『日本人の勝算』デービッド・アトキンソン(東洋経済新報社)
人口減少時代における日本の活路とは何か。外国人著者ならではのシビアな視点で、日本の弱点と希望を見
出す一対の本。
2.『我が投資術 市場は誰に微笑むか』清原達郎(講談社)
個人資産800億円超のヘッジファンド創業者が、その驚異的パフォーマンスの裏側を明かした注目作。「投資は心理戦だ」と言わんばかりの迫力に、思わず読み入ってしまいます。
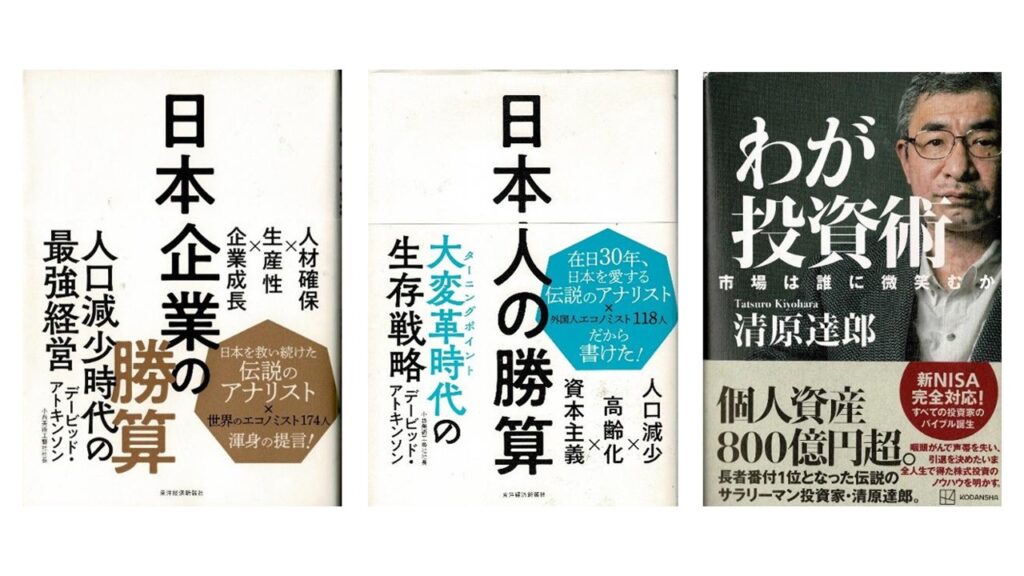
Dさんの問い:退屈ってなんだ?
Dさんの紹介は哲学書ながら、20万部超えのベストセラー。
『暇と退屈の倫理学』國分功一郎(新潮文庫)
テーマは「人間にとって退屈とは何か」。暇や退屈にどう向き合うかを、古代から現代の思想を縦横無尽にたどりながら考察。
結論は「退屈を楽しむ力=人間であることの証」。言い換えれば、ただの“暇つぶし”が実は高等な営みなのかもしれません。答えを急ぐのでなく、考える過程こそが楽しい──そんな読書体験を教えてくれる哲学入門の好著です。
Eさんの視点:料理人は人生のマルチタスク
『料理人という仕事』稲田俊輔(ちくまプリマー新書)
料理好きが高じてお店を持つ夢を描く方にも、現場のリアルを知りたい方にもおすすめ。著者は南インド料理の名店「エリックサウス」オーナー。
厨房の裏側には、仕入れや原価管理、接客、掃除まで含めた“地味な積み重ね”がある。そうした「地味だけど避けて通れないこと」をしっかり語ってくれるところに、共感と敬意が集まりました。
Fさんの涙:小さな命の“死にざま”に学ぶ
『生き物の死にざま』稲垣栄洋(草思社文庫)
セミ、カマキリ、マンボウ、チョウチンアンコウなど29の生き物の最期の姿に焦点をあて、生と死を見つめるエッセイ集。
読みながら思わず電車で涙が…というFさんの言葉に、全員が静かにうなずきました。わかりやすい文章で、生き物たちの命の物語が胸に迫る一冊です。
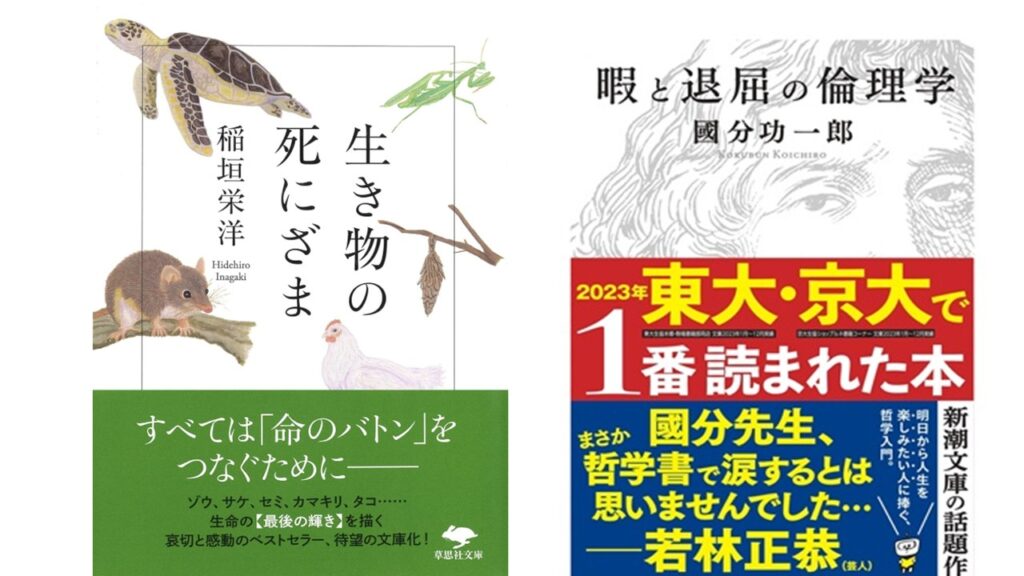
Gさんの二冊:カタツムリと果物で世界を語る
1.『歌うカタツムリ』千葉聡(岩波書店)
サブタイトルは「進化とらせんの物語」。カタツムリの進化から始まって、生物の進化論、さらには哲学的な問いまで、螺旋のように展開していく一冊。進化論を支えた日本人研究者たちの功績にも触れられています。「ネオダーウィニズムに代わる進化の見方が見えてくる」とGさん。学問の奥深さと、進化する知の面白さが詰まっています。
2.『日本の果物はすごい』竹下大学(中公新書)
戦国時代から現代まで、果物が日本の文化と経済にどう関わってきたかを語る軽妙な一冊。懐かしい果物から、統計データの裏側まで、読み方は人それぞれ。「自分の出身地の果物が何か、あらためて調べてみたくなる本です」とのことでした。
それぞれの本が、それぞれの視点から、人生・社会・自然を照らしてくれる。
そんな豊かな時間をみんなで共有できたことが、何よりの喜びでした。
次回の読書会8月29日(金)13:00~
次々回は9月26日(金)13:00~ テーマ本は、自分の好きなor読んだ、宮沢賢治の本についてです。
どんな話が飛び出すか、どうぞお楽しみに!
(文責 正田、小原)


コメント