第10回 八雲PC読書会
開催日時: 2025年10月31日(金)13:00~15:00
開催場所: 八雲倶楽部
出席者: 8名
――人生・文明・自然をめぐる六つの本――
今回の読書会は、まさに“多彩な人生と地球のドラマ”を読み解く回となりました。
介護、絶滅、旅、文学、虫、そして水道――一見ばらばらのテーマのようでいて、どの本にも共通していたのは「生きること」「つなぐこと」へのまなざし。
6人の紹介者から次々と熱のこもった発表があり、笑いと共感、そして考えさせられる時間が流れました。
以下にそれぞれの紹介をまとめます。
『介護未満の父に起きたこと』 ジェーン・スー著(新潮新書)
人気コラムニストのジェーン・スーが、別居する高齢の父の世話に奮闘した5年間をユーモアたっぷりに綴ったエッセイ。“介護未満”の現実をリアルに描きながら、離れて暮らす娘と父の距離感や、加齢に伴う「維持する生」の大切さを浮き彫りにしています。読者は、現代社会の長寿時代における「老いとの付き合い方」を改めて考えさせられます。
読書会では、「身につまされる」「もう介護される側が近い」との声も。さらに「不道徳な父とは!?」というツッコミから、「介護保険外で月50万円の24時間介護ができる」という発言まで飛び出し、「それは1%未満の富裕層の話だ!」と議論が白熱。笑いとため息が交錯する20分となりました。スー流の軽やかな筆致が、介護を“悲劇ではなく生活の一部”として描いたことに、多くの共感が集まりました。
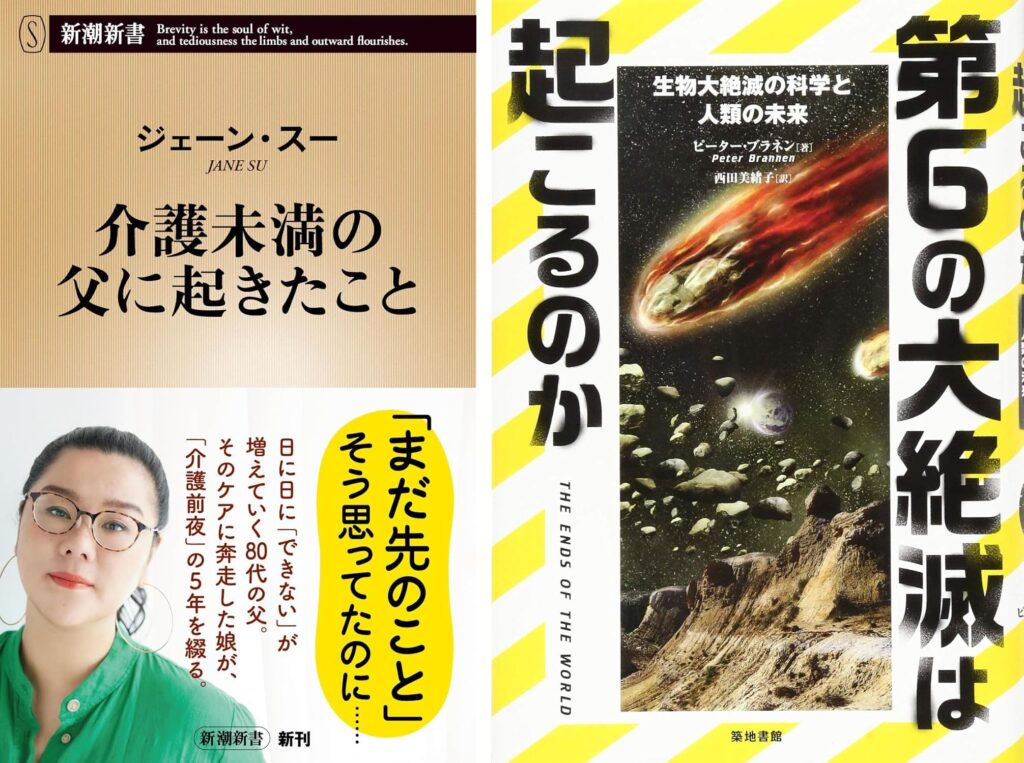
『第六の大絶滅は起こるのか』 ピーター・ブラネン著(築地書館)
地球46億年の歴史に刻まれた「五度の大絶滅」を科学的にひもとき、次に来る“第六の大絶滅”が人類自身によるものではないかと警鐘を鳴らす本。火山活動、寒冷化、小惑星衝突――壮絶な地球のドラマの末に生き残った私たちが、今や最大の環境破壊者になっているという現実を突きつけます。ペルム紀末の絶滅では海洋生物の96%が消滅したという記述に、会場からはどよめきも。
「人類は滅亡に向かっているのでは?」という悲観論が多く出る一方で、「地球は5回もリセットを経験してきた。きっとまた再生できる」との楽観的な声も。議論は“地球は助かるが人類はどうか”という哲学的な方向にまで及びました。最後は「せめて次の絶滅を“見届ける側”にはなりたくないね」「自分の生きている間には起きない」と無責任な意見も、壮大なテーマながらも色々な余韻を残しました。
『ヴェルヌの『八十日間世界一周』に挑む ― 四万五千キロを競ったふたりの女性記者』 マシュー・グッドマン著 金原瑞人・井上里訳(柏書房)
1889年、ジュール・ヴェルヌの小説を現実で再現しようと、二人の女性記者が東回りと西回りで“世界一周競争”に挑んだ。新聞社の販促企画とはいえ、女性が単独で地球を旅するというのは当時前代未聞。蒸気船と鉄道を駆使して世界を駆け抜ける姿に、文明の躍動と女性の解放が交錯します。旅先の描写も生き生きとしており、特に日本滞在の章では「我もアルカディアにありき」という詩的な一文が印象的。
読書会では、「日本を高く評価しているのがうれしい」「髷の描写は本当?」と盛り上がり、「兼高かおるの“世界早回り」のはなし”を思い出したという声も。女性二人の生き方の対比を通して、19世紀末のジャーナリズムや社会の価値観までも映し出す一冊に、会場は旅気分と文明論の双方で沸きました。
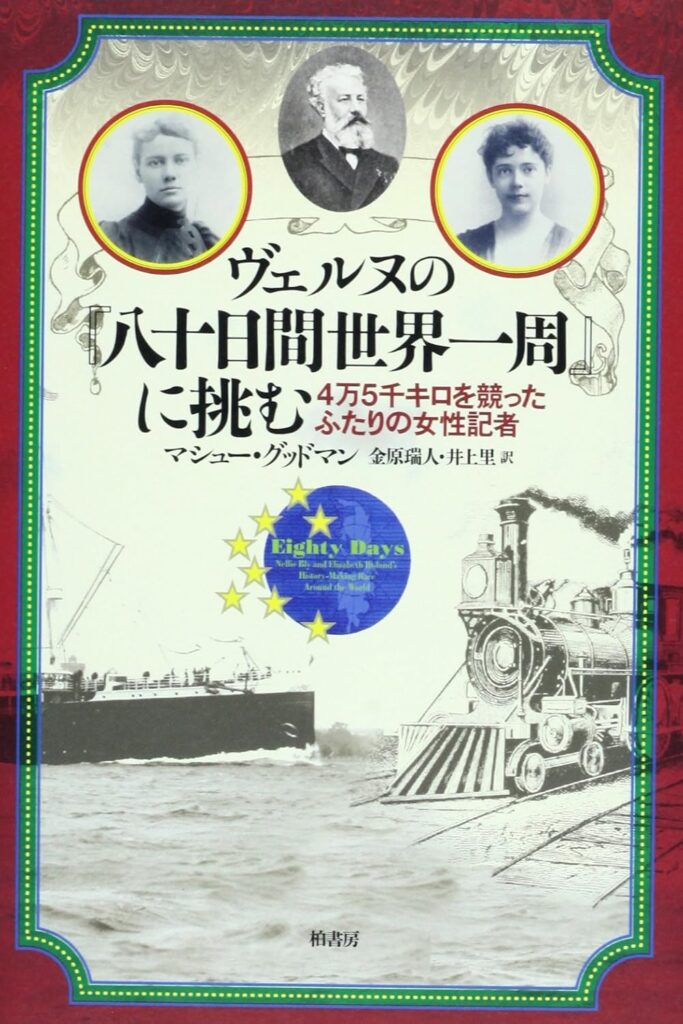
『文学は何の役に立つのか?』『本心』 平野啓一郎著(岩波書店/文春文庫)
現代文学を代表する作家・平野啓一郎の二冊を合わせて紹介。エッセイ集『文学は何の役に立つのか?』では、文学を“他者を通して自分を考える装置”と捉え、AIやSNSが支配する現代における「共感と自由」の意味を語ります。文章は端正で読みやすく、文学が人間の尊厳を守る最後の砦であることを静かに説いています。
一方の小説『本心』は、2040年の近未来を舞台に、亡き母の「ヴァーチャル・フィギュア」を通して“死ぬ自由”や“他者との関係”を問う物語。主人公が母の「もう十分(生きた)」という言葉の真意を探る過程は、まさに“心の哲学”そのものです。読書会では、「母の“本心”とは何に対してなのか? 死か、愛か、それとも人生そのものか?」という問いが交錯。平野の提唱する“分人主義”(人は複数の人格を持つ)にも言及があり、「本心はひとつではない」という結論に多くの共感が集まりました。文学がいまなお人間の心を支える力を持つことを感じさせる紹介でした。
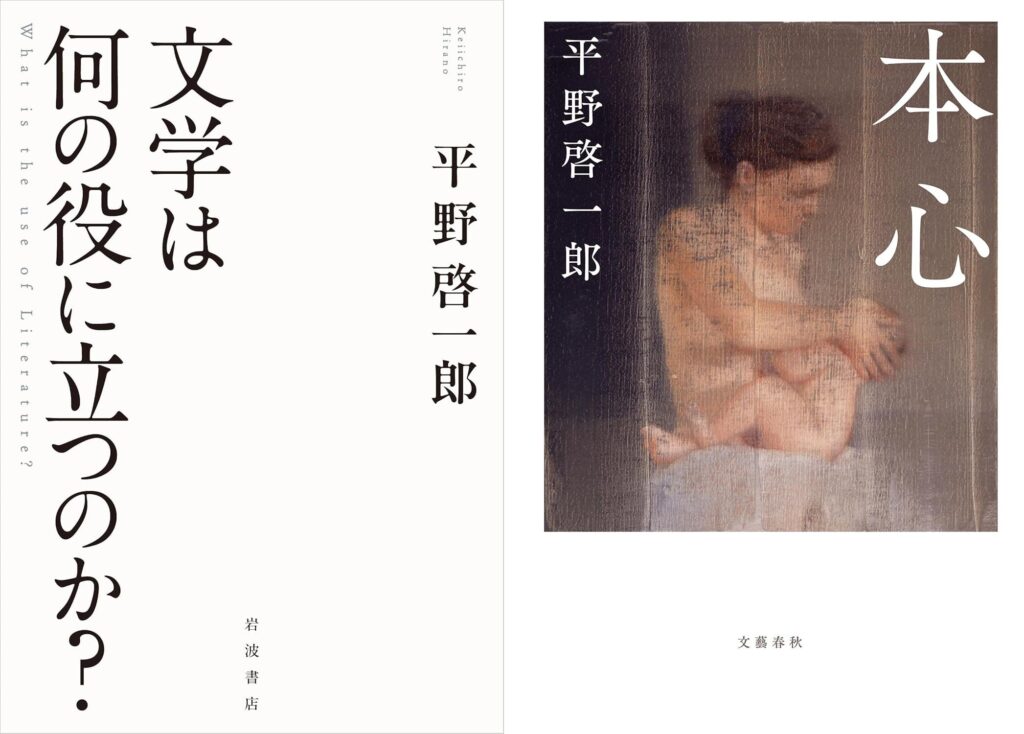
『ファーブル昆虫記 完訳 第1巻上』 ジャン=アンリ・ファーブル著 奥本大三郎訳(集英社)
スカラベ(聖なる糞ころがし)やアナバチなど、虫たちの生態を観察と詩情で綴った名作『ファーブル昆虫記』。訳者・奥本大三郎が「耳で聴いてわかる日本語」にこだわり抜いた完訳版は、科学と文学の融合そのもの。自然への敬意と好奇心に満ちています。
紹介者にとっては“人生最初の読書体験”。半世紀を経て再び手に取り、少年時代の胸の高鳴りを思い出したと語ります。読書会では「日本人の虫好きはファーブルの影響かも」「鈴虫やコオロギを鳴かせて遊んだね」「中国ではコオロギを戦わせるらしい」と話題が広がり、シートン動物記の思い出まで飛び出しました。虫の世界を通して、子どもの頃の純粋な好奇心と“いのちの不思議”を思い出させてくれる一冊でした。

『江戸・東京 水道全史』 鈴木浩三著(筑摩選書)
江戸と東京を「水道」という切り口で貫いた力作。神田上水・玉川上水の開削から、地形・制度・経営・財務システムに至るまで、水の流れが都市の骨格を形づくってきた歴史を描き出します。著者は東京都水道局勤務を経た経営史家であり、その実務経験に裏づけられた分析は圧倒的。まさに「都市経営としての水道史」です。
地形図や古地図をもとにした上水のルート解析は圧巻で、江戸城の地形や神田川・玉川上水の整備過程が生き生きと蘇ります。読書会では「知識の厚みと実証の正確さがすごい」「父・鈴木理生氏の研究を継承しつつ、新しい発見も多い」と絶賛の声。地図を片手に読む人、すぐ図書館に走った人もあり、専門書ながら熱い関心を集めました。“水の都・江戸”を築いた人々の知恵に、改めて敬意を抱かせる一冊でした。
今回の読書会は、現代社会から地球史、近未来、江戸の上水まで、まさにスケールの大きな読書旅でした。
どの作品も、私たちが「どう生き、どうつながるか」を問いかけています。笑いあり、感嘆あり、しみじみとした沈黙もあり――読書会の魅力がぎゅっと詰まった回でした。
次回もまた、ページをめくるごとに世界が広がる――そんな“知の旅”を楽しみにしています。
文責 正田、小原
次回 11月28日(金)13時~ 『国銅』 帚木蓬生 新潮文庫
次々回 12月26日(金)13時~ 修了後、忘年会予定(任意参加)


コメント